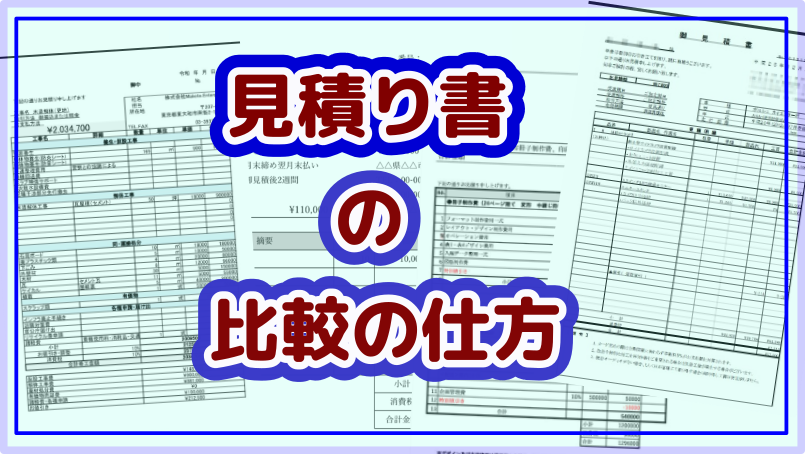昨今見積りを取るといえば、ほとんどのお客様が複数の業者から見積りを取って、見比べてから業者を決めることが多くなっているように思います。
そのことは業者を選ぶための大変良い方法ではありますが、明確な選考基準のないままの比較では、単に価格の”高い””安い”だけの比較になってしまい、「良い業者を選ぶ」という目的からは少し外れてしまうのでは…と、感じることがあります。
見積り書の見方
見積り書を比較するには、「どこに」(塗装箇所)「何を」(塗料の種類や材質、メーカー名等)「どのように塗って」(下地調整を含む塗装工程)「総額幾らなのか?」を知ることが肝心です。
このことを確認もせずに、”金額の安いところは信用できない”、”高いところはダメ!” ”中間の値段の業者”に決めよう…!!
では、良質な塗装や、良い業者との関わりのない決論に達してしまう恐れがあります。
そこで、ご自分の家を塗り替えるのに、どんな塗装工程が必須で、どんな塗料でどのように塗り替えようとしているのかを正確に知るための、具体的な塗装工程や塗装方法などを羅列いたしましたので、これらを参考に見積り書を検討していただければと思っています。
足場
まず第一番は足場です。足場なしで塗れるのは手の届くところだけで、ほんの狭い範囲に限られますので、建物全体を塗装するには平屋の家であろうと足場は必須です。
飛散防止用シート
次に必要なのが、足場にかける飛散防止用のメッシュのシートです。これなしで洗浄や塗装をしては、ご近所に迷惑をかけるばかりなので、これも必須です。

高圧洗浄
次いで屋根や外壁全体の高圧洗浄です。屋根についたコケやカビ、藻類をこそげ落としたり、外壁の汚れや青苔などもすべて洗い流してから塗装をしないと、塗膜の剥離につながってしまいますので、これも必須です。

ビニール養生
洗浄後に行われるのが、塗らないところや、塗れないところ、汚せないところを覆うビニール養生が必要です。
そのほかに、塗料が垂れても床を汚さないようにするための敷物などの養生も必須です。
下地調整
ここまでくると、人数にもよりますが、屋根塗装があれば屋根のひび割れや、棟板金の釘の飛び出しの打ち込み、板金をケレンしてさび止め塗料を塗布したりといった下地処理作業に入ります。
勿論それと同時に、外壁のひび割れの補修などの下地処理作業も並行して行なわれます。
ただし、サイディングの目地のコーキング剤の打ち返しが必要な場合は、養生をする以前に劣化したコーキング剤を取り除き、新しいコーキング剤を充填したのちに、時間をおいてからビニール養生をすることになります。
ここまでくれば、いよいよ塗装工程に入ります。
下塗り
屋根も外壁も上塗り塗料とのマッチング、現状の下地状況を考慮した下塗り塗料を選択して、下塗り塗料を塗布します。
中塗り(上塗り塗料の1回目)
下塗りの次は中塗りですが、中塗りと言っても特別な中塗り用の塗料があるわけではありません。
中塗りというのは、お客様が選んだ上塗り塗料の1回目(下塗りから数えると2回目)の塗装をすることを言い、3回塗りの中間にあたることから、便宜上中塗りと呼んでいます。(外壁、屋根共通です。)
ここで肝心なのは、隅から隅までもれなくきちんと3回塗りされなければならないということです。
どういうことかというと、中塗りと上塗り塗料を同じ色で塗り重ねると、多少の塗り残し、または故意に塗らない部分があっても気づくことができないということが生じてしまいます。
そこで考えられたのが、2回目の中塗りの色を上塗り塗料の色と違うものにするということです。
こうすると、塗り忘れた部分などはすぐに発見することができますので、隅々まで間違いなく3回塗りすることができますので、色替えをするのかどうかの確認をすること大がとても切です。
上塗り(上塗り塗料の2回目、合計3回塗り)
上塗りは、仕上げとなる最終塗装ですから、塗り残しとか、塗りムラなどができないよう、慎重な塗装が望まれるところです。(外壁、屋根共通)
付帯物塗装
外壁や屋根の塗装が終わればすべて終了…!ではありません。
外壁に付帯している、雨樋、破風板、軒天、霧除け、戸袋、雨戸、幕板、シャッターBOX…等々が残っています。
実は、この付帯物の塗装を意外と軽んじる傾向があるのを残念に思っています。
例えば、付帯物をすべてを1液塗料で済ませてしまい、それも、外壁の塗料よりも劣る塗料で仕上げることになっていたりすることが、当たり前のようになっていることがあります。
ちなみに1液塗料も2液塗料も仕上がりだけなら大差なく見えるものです。
そうした塗料のグレードなどのチェックも重要です。
塗料の詳しい解説は「塗料の種類や、材質、機能」をご覧ください。
一式…って!??
見積り書に、一式幾らという表示をご覧になったことはありませんか?
面積や長さの記載がなく、ただ一式なんて書かれていると、なんだかいい加減な感じを受けることがあるかもしれません…。
けれど次のような写真をご覧ください。

この写真の家には数多くの付帯物が付随しています。
「破風板」「軒天」「戸袋」「雨戸」「雨樋」「木製の窓枠」「霧除け」「窓手すり」「面格子」などがありますが、これらを一つ一つを面積や長さを数字で示すことが正確でしょうか?
それよりも、下の写真のように写真上にこれらの一つ一つに引き出し線をつけて、その部署を何でどのように塗るかを示したほうがはるかにわかりやすく、正確で間違いのない方法だと思うのですが…。

当社ではこのような方法をとらせていただいて、付帯物塗装費を一括して一式幾らという記載をさせていただくことがあります。
木部塗装
木部が付随している住宅というのは、下の写真のような住宅で、破風板、軒天、戸袋、窓枠、霧除け、濡れ縁、のほか、各窓にはまっている面格子などがあります。


これら「木部」は、当然ながら外壁と同じように、ケレンをして木部用の下塗り材を塗布したのちに、上塗り塗料を2度塗りしますが、「木」というのは、湿気と乾燥を繰り返すことで伸縮、変形します。
そのため、塗料はその変化についてゆくことができず、どうしても外壁と比べると持ちが悪くなります。
おおよそですが、木部の塗装は、外壁に塗った塗装の約半分程度の持ちと考えて外壁用塗料を選択しないと、数年後、外壁の塗装だけはしっかりしているのに、木部の方は先に剝がれてしまって…、木部だけを塗るのにまた足場をかける羽目になった…という例が少なくないからです。
一方、木部を伴わず、雨樋や板金類しか付帯物のない下の写真のような家もあります。

このような家の場合、付帯物塗装面積は木部を伴う家より少なくなりますが、逆に外壁の塗装面積が多くなります。
ウッドデッキ
ウッドデッキの塗り替えは、屋根がついていない場合と、ついてる場合では塗り替え周期に大きな差が出ます。
木部塗装で述べたように「木」は湿乾差で、伸縮、変形するだけでなく、放置して置くとすぐに腐食してしまいますので、外壁の塗り替え周期の倍ぐらいの頻度で、防腐剤の入ったオイルステインや撥水塗料での塗り替えが必要になります。
鉄部塗装
鉄部塗装と言っても、最近の住宅ではそのほとんどが板板金加工されたもので、霧除け上部の板金や、水切り用の板金、そのほかには雨戸やシャッターボックス、換気扇用ダクト、そのほか住宅によってはトタンの下屋根が含まれることもあります。
こうした板金類の塗装は、言うまでもなくケレン・錆止めといった下地調整が重要ですが、比較的新しい板金の場合は、表面をサンドペーパーなどで目粗しをして、塗料の食いつきをよくしてから塗装することも大切です。
木部にも鉄部にも属さない付帯物
「鉄」でも「木」でもない付帯物というと、ステンレス、アルミ製品、銅板、樹脂加工品…などがありますが、基本的にはこれらは塗装対象外です。
ただし、雨樋などの塩ビ製品には塗料が食いつきますので、付帯物塗装費に含まれます。
こうした塗装対象外のものの塗装を希望される場合は、見積り時の相談が必須です。
それなりの下塗り剤の用意が必要だからです。
防水塗装
本格的な防水工事をするには、専門の防水屋さんによる別途見積りが必要になりますが、ここで取り上げるのはベランダの(防水トップコート)塗装のことです。
最近のベランダの防水のほとんどがFRP(繊繊強化プラスティック)防水で、築10年前後での塗り替え時には、防水表面(トップコート)だけが傷んでいることがほとんどです。
そこで、その表面(トップコート)の塗り替えが必要になります。
そのトップコートの塗装工程は、高圧洗浄を含めたケレンなどをしたのちに、アセトンシンナーなどで床全体を拭き取り、FRP用プライマーを下塗り、防水用トップコートを2度上塗りして仕上げます。


建物本体以外の塗装
建物本体以外の塗装箇所というと、フェンス、塀、物置、車庫…などが考えられますが、これらについては見積り時にお客様の意向を伺ってからの見積りとなります。
これらの塗装で、業者が一番困るのは、全体の塗装が終わってから”やっぱり、あそこも塗ってほしいんですけど…”です。
車庫やフェンス、塀も塗装工程は建物本体となんら変わりません。
ですから、何を塗るにしても、養生、ケレン、下塗り、中塗り、上塗りの工程が必須です。これを本体完了後に塗るとなると新たに3日から4日が必要になってしまいます。
こうした双方にとってリスクのあることを避けるため、是非、見積り時にご相談いただきたいと思います。
本体以外の別途見積りになるものもありますが、無料のサービス塗装ができるものもありますので、遠慮なさらずに事前に相談なさることをお勧めいたします。
塗装後に発生する費用…!?
えっ、塗装が終わった後にも発生する費用なんてあるの…?
と、思われるのは当然ですが、実際にはその費用はどの業者にも必要不可欠なものです。
塗り残し、汚れ等々がないかを点検したのち、養生を取り払い、足場も解体して、清掃も終わると、塗装工事完了となりますが、このときに発生したゴミや半端に残った塗料などは、産業廃棄物として、有料で処分する必要があるので、どの業者にも廃材処理費が発生してしまうのです。
まとめ
以上、足場架けから足場の解体までの塗装工事に必要な項目を挙げてみましたが、この項目がどの業者の見積り書にも全て記載されているというわけではありません。
見積り書(あるいは提案書)というのは、単にその家の塗り替え費用を提示するだけでなく、その業者にとって、お客様への大切なプレゼンテーションの役目を担っているからです。
見積り書で仕事が得られるかどうかが決まってしまうのですから、どの業者も見積り書に神経をとがらせるのは言うまでもありません。
そこで、ある業者はここで示した項目よりもたくさんの項目を設け、細分化させることで、この業者は”きちっとしている…”といった印象を狙ったり、他の業者は逆に養生費などの項目を立てずに”安すさ”をアピールしたり…などの工夫がなされたりすることがあります。
けれど、どんな形式の見積り書であろうと、先に示した工程が必須であることに変わりありません。
見積りには正確な塗装面積が必須…!?
また、一般的に見積り書は、塗装面積や長さに単価を掛けて算出します。
ですから、塗装面積が間違っていては、当然ながら費用に大きな差が生じてしまうのは言うまでもありません。
ですが、多くの塗装業者(弊社も含めて)のチラシなどには、一定の大きさの家を対象に、その家を丸々塗ったら幾らといったパック料金が表示されています。
これは一般的な住宅の場合、ほぼ同じ大きさの家では外壁面積も屋根の面積もそう大きな差がないことから、いわゆる一式価格(パック料金料金)で表示することが可能なのです。
そこで問題になるのが、どんな塗料で、どう塗ると幾らなのかのか!ということです。
これが見積り書を検討するとき最大の重要課題なのです!!
3社から見積もりを取ったら、三者三様の面積でどこが正しいのか解らないといったようなことはよくあり得ることです。
その時に大切なのは、どこが正確な面積なのかを探るのではなく、先ほど述べた塗料の材質や種類が何なのか?、どう塗るのか?などを吟味比較することこそが重要なのです。
なぜなら、外壁を一番大きく見積もった業者も、一番小さく見積もった業者も外壁をすべて塗ることに変わりないからです。
例えば雨樋の長さを、ある業者は30メートルと見積もったのに対し、他の業者は15メートルと見積もったからと言って、15メートル分しか塗らないなどということはないからです。
正確な塗装面が必須なのは、ビ、ルやマンション、病院といった大規模塗装工事の時です。
大規模塗装工事と戸建て住宅では、それにかかる足場の規模、塗料の量、工事に携わる職人の数、日数すべてが桁違いなので、正確な面積や長さの計測が必須なのです。
それと大規模塗装工事の場合、ほとんどが事前に塗料の種類や塗装工程が決まっていますので、塗装面積×平米単価で得られた総額だけが競われることになるので、戸建て住宅のようなその他の検討の余地が少なく、正確な数字が必要になるのです。
見積書を比較するときは、是非このようなことを念頭に置いて比較なさることをお勧めいたします。